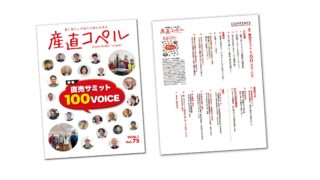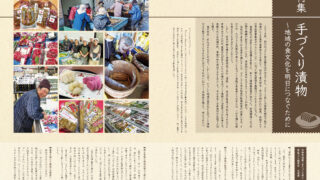生産から加工、流通、そして消費者へ。
LFPながので信州の食料システムをつなぐ。
目次
・LFPながの第1回研修会を開催しました
・第1回研修会 議事録
LFPながの第1回研修会を開催しました
6月24日(火)にLFPながののキックオフとなる第1回研修会を開催しました。オンライン参加者を含む49名のLFPパートナーや関係者が出席しました。
①本年度のLFP長野のメインテーマを「中山間地における遊休荒廃地の拡大防止」とすること
②「アップサイクル」「信州産小麦の利用と栽培の拡大」「エノキタケの需要拡大」等、サブテーマに関するテーブル(=情報交換の場)を並行して持つこと
③メインテーマのもとに開発補助金を利用した商品開発プロジェクト、地域型協調領域実証の取組を進めるべくアイデア掘り起こしを行うこと
――などが全体で確認されました。

第1回研修会 議事録
(発言者敬称略)
1.開会(14:00)
事務局より本日の進行と趣旨を説明。
2.あいさつ(14:05〜)
【発言】長野県農政部農産物マーケティング室長 城取和茂
物価高による資材コスト上昇で農家経営は厳しい状況にある。「再生産可能な適正価格」の必要性が消費者にも浸透しつつあると指摘。ぜひ長野県産農産物を選択し生産者を支えてほしいと参加者へ呼び掛けた。LFPながのの過去成果(キノコ消費拡大、摘果リンゴ活用、県産小麦拡大など)を紹介し、多様な主体が知見と技術を持ち寄って地域課題をビジネス化する意義を強調。「限られた時間だが有意義な研修に」と結んだ。
3.昨年度実績・本年度方針(14:10〜14:40)
【発言】(株)産直新聞社 社長 毛賀澤明宏
2024年度までの成果と課題を振り返り、今年度の重点テーマを中山間地の遊休荒廃地の拡大防止として提案。年間8回程度の課題検討会と2回の地域戦略マッチングでプロジェクトを具体化する工程表を提示した。
4.講義(14:40〜14:55)
【発言】全国プラットフォーム事務局((株)船井総合研究所)伊藤順
改正農業・農村基本法により「持続可能な食料システム」確立が求められた背景と、サプライチェーン全体で価値を共有する連携の必要性を解説。
【発言】LFPながのコーディネーター オガル(株)執行役員 小関大輔
イノベーション創出の鍵として「知識の組み合わせ」「遠い関係の活用」「良いミーティング」を提示し、オープンマインドな議論を促した。
5.自由討論(15:20〜15:55)
5-1.ソルガム利用拡大プロジェクト
【発言】信州大学工学部 天野良彦特任教授
(株)長野サンヨーフーズ 椻下剛
天野教授は、中山間地でソルガムを「食・エネルギー・堆肥」に循環利用するモデルを二十年研究。契約農家は七十〜八十戸に拡大したが、本格運用には桁違いの作付け増が不可欠と説明。品種多様性を生かせば小麦代替や機能性素材など幅広い応用が可能と紹介した。
椻下氏は自社製ソルガムミルクを提示。グルテンフリーでポリフェノール由来の渋味を持つ茶褐色の液状原料で、ビール・カレー・ラテ・ジェラートなど試作済み。今年度は食品メーカーや小売と連携してBtoC商品を量産し、市場拡大を目指すと表明。
質疑応答では栽培面積拡大策、収穫機械、価格、栄養価などが問われ、天野教授が技術・経済面の課題と解決方向を回答した。
5-2.中山間地メタンガス低減・棚田酒米プロジェクト
【発言】合資会社宮島酒店 代表社員 宮島敏
(株)Wakka Agri 社長 細谷啓太
信州大学農学部 齋藤勝晴教授
宮島氏は伊那市高遠・長谷地区での環境配慮型酒米栽培と酒造りを紹介。水田メタン削減に有効な「中干し延長」が酒米品質維持と相反する課題を抱えるが、冷涼な中山間地条件を活かし、環境負荷低減と高品質両立を図る計画を説明。削減分をJクレジット化して事業者間で価値共有するモデルを構想した。
細谷氏は農家として参加し、中干し延長による雑草発生や収量変動を実測してリスクを数値化したいと提案。Jクレジット収益を農家に還元する仕組みの必要性を指摘した。
斎藤教授は、地域条件と栽培方法でメタン発生量は大きく変わるため、中山間地・有機栽培の実測データは学術的にも貴重とコメント。大学としてガス計測と微生物解析を行い、科学的根拠に基づく削減手法を提示する意向を示した。
5-3.地場産食材を活用した防災備蓄品開発プロジェクト
【発言】(株)マツザワ 専務 森本康雄
能登半島地震を契機に「長野県産原料・県内加工の防災備蓄食品」を構想。県産米と県産肉を用いた五年常温保存レトルトリゾットを主力候補とし、自治体・学校給食のローリングストックで廃棄ロスを減らし、地域内経済循環を生む仕組みを提案。原料生産者、加工業者、流通、小売、行政との協働を呼び掛けた。
質疑で(株)大福食品工業が県産原料によるアルファ化米製造を提案し、森本氏は共同開発に前向きな姿勢を示した。
5-4.県産小麦需要拡大
【発言】長野県学校給食会 専務理事 瀧本英一
県産小麦100%パンを継続して提供することで、小麦の生産拡大への期待を述べた。
【発言】柄木田製粉(株) 田部井ひろ美
昨年度実施された茅野市永明小学校での地産地消授業を紹介し、子どもの学びの場を広げたいとコメント。
【発言】(株)中部発展商事 社長 佐東力
昨年度の県産小麦ドーナツ事例を報告。
5-5.エノキ・キノコ関連商品拡充
【発言】(株)大福食品工業 新井愛美
エノキタケメンチカツを学校給食へ広げた実績を踏まえ、ソルガムやジビエを掛け合わせた新商品の可能性を提起。
【発言】(株)中部発展商事 佐東氏
昨年度試作したキノコミックスパスタなどを再チャレンジする意向を述べた。
6.行政コメント(15:55〜16:00)
【発言】農林水産省 大臣官房新事業・食品産業部企画グループ 企画官 藤原稚佳子
今年度から始まった「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業」がこれまでのローカルフードプロジェクトを発展させた枠組みであると説明。「持続可能な食料システム」を改めて強調し、討論で示されたアイデアがサプライチェーン全体を見据えた課題解決に向かっていると評価した。
7.閉会(16:00)
次回「第1回課題検討会」を7月8日(火)17:00、伊那市+オンラインで開催予定と案内し散会。