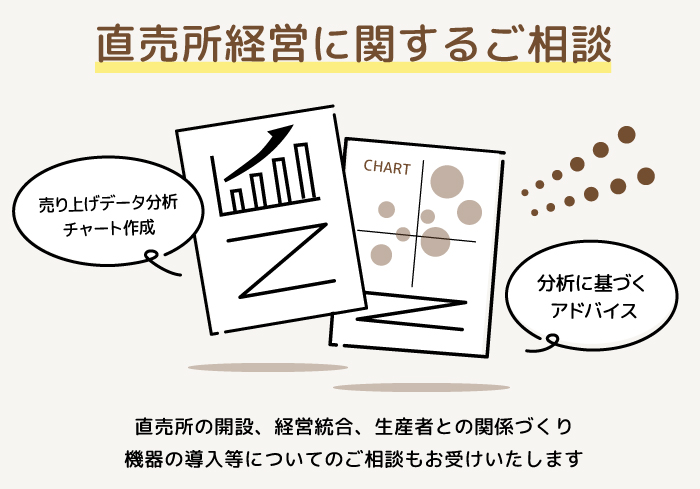文・毛賀澤明宏(『産直コペル』編集長)
全国各地で大型直売所※の建設ラッシュが続いている(※東北地方では「産直」とも呼ぶが、本稿では一律に「直売所」と表記する)。行政主導の道の駅開設に伴う直売所の設置、各地のJAによる大型ファーマーズマーケットの開設、民間資本による〝農と食のワンダーランド〟施設の建設……など、様々なパターンがある。中には優れた地域づくりの成功事例になっているものもあり、それらをすべて一括りにして論ずる心算は毛頭ないが、それでも、近年開設された大型直売所の多くで、「これが直売所なのか?」「これが地方創生・地域振興と言えるのか?」と思わざるを得ないような事態が生み出されていることが多い。
本稿では、大型直売所建設ラッシュの中で生起している問題とその根拠を整理し、今後進むべき道を示したい。
なお、経営の内情に踏む込むことにもなりかねないので、直売所の名称や存在地域については伏すことにしたい。
箱を作り、仕切りを提示するだけの即席パッケージ型直売所づくり
全国各地の直売所を訪問して歩いていると、本当に「何のためにこんな大きな店を作ったのか?」「どういう議論をして開店に備えてきたのか?」「なぜ、もともと採算の立ちそうもないレストランを当たり前のように併設したのか?」……などと、正直、憤り交じりに言いたくなる新設大型直売所に出会うことが多い。すでに建設済みで開店しているものはもちろん、今まさに建設中のものや建設計画中のものであっても、建物やそれを使った事業計画の概要を聞くと、同じように感じることが多い。
誤解されないように繰り返し言うが、筆者は大型直売所全般を一括りにして良い悪いと判定する意図はない。新設大型直売所でも、優れたコーディネーターや開設リーダーの指導で、あるいは優れた店長や現場スタッフの創意で、見事に地域の農業振興の拠点となっている(なりそうな)店もある。

だが、そうではないパターンの方が、残念ながら圧倒的に多いのだ。例えば―
Z県のN直売所は、当地のJAがオープン初年度4億円ほどの売上げ目標を掲げて開設した。生鮮三品が揃い、農家レストランを併設した複合型の大型施設だが、オープン直後から肝心かなめの地場産農産物が集まらず、それを補うために市場仕入れ品を多く並べたため、ますます地元農家の心が離れて地元産品が少なくなっていくという「負のスパイラル」が生じた。売上げ目標の半分にも届かないという状況が続いている。
Y県のM直売所は、道の駅の開設に合わせて同地区の自治体が施設を作り、自治体・商工会議所・地元企業などが出資して作った第3セクターが運営する形でスタートした。直売コーナー、土産品コーナー、フードコートなどがあり、「相乗効果で売上げ向上」を目指したが、そもそも農家が農産物を少ししか出荷しなかったことから客足が伸びず、もっぱらB級グルメ(のようなもの)を〝ウリ〟にして集客するしか手がなくなっている。もちろん売上げ額は目標を大きく下回っている。
これらと似たような事例は、実は、全国各地にびっくりするほど多くある。「JAは農家の代表だ」という独りよがりの自負に酔いしれているからなのか、もしくは、「農家に経営のことは分からない」などと自営業者の上から目線で農家を見下しているからなのか、とにかく当該地域の生産農家に直売所開設の目的と計画を繰り返し伝え、頭を下げて協力と出荷を訴え、出荷者のグループを下から組織する苦労を積み重ねずに、箱=建物を建ててしまった結果、こういう事態が生み出されてるのだ。
長い苦労を重ねて現在では大きな売上げを誇るようになった著名な複合型直売所の事業領域や運営方法をコピーして、そのまま移植すれば、〝儲かる直売所が〟できる―こういう安直な考え方が根底には横たわっているのである。

大型直売所を支える人と組織の育成の欠落

このパターンの最も粗悪なものに先日出くわした。まだ道の駅の建設計画の段階にあるⅩ県のL地域のこと。
道の駅を「地域の人々が寄り添い、力を合わせ、地域を創る拠点」にしようと奮闘している地元農家と商工業者がいるのだが、彼らが道の駅・直売所の位置づけ・目的・完成イメージなどをめぐる住民内部での議論の活発化を求めるのに対して、自治体が契約を結んだ中央の(未経験な)コンサルが「そんなことは無駄」と言い放ち、「そんなことより繁盛している店を見に行けば問題は解決するはず」などと、もっぱら当該コンサルが尊敬する別のコンサルタントから指導を受けるように話を引っ張っていこうとしているのだという。ここまで行ってしまうと、もはや何のために道の駅・直売所を開設しようとしているのか?何のためにコンサルしているのか?そのこと自体が疑われてしまう。
ここまでひどくはないものの、W県のO直売所のような、そこで〝働く人〟をいかに育成するかという問題を蒸発させた新組織建設の事例はかなり多くの地域に存在する。
このO直売所は以前より数億円の売上げを誇る繁盛店舗だったが、施設の老朽化などもあり、さらに大きな売上げを目指して抜本的な増築リニューアルを行った。160%増というビッグな計画だ。ところが、こうした計画は、JAから委託されたコンサルタントが、一握りの経営陣と話をしただけで、これまた別の繁盛店の事業構成を完全コピーして作った、いわゆる「固有名詞だけを変えればどこでも通用する」ものだった。
その店を支えて働いている直売所スタッフ(特に正社員ではないが重要な役割を果たしている人など)からはたったの一度も意見聴取をせず、ましてや出荷生産者からの改善要望なども集約することさえせずに、リニューアル計画なるものが作られて、それに基づいてリニューアルがなされたのである。
これでは直売所スタッフにやる気が湧くわけがない。リニューアルオープンしても、挨拶の声も聞こえてこない殺風景な店になり、常連客は口をそろえて「前の方が良かった」と噂するという悲惨な事態が生まれてしまった。もちろん売上げ目標は達成していない。

店を新しくする、活性化するということは、そこで働く人々の意識を覚醒させ、働く意欲を増大させ、働く人々の組織体制を刷新することなしにはできるはずがない。こんな当たり前のことが、しかし、直売所のリニューアルや新設などにおいては考察の埒外に置かれていることがある。働く人々には何も話が下ろされず、蚊帳の外に置かれたままで施設が新しくなるのである。これはO直売所だけの話ではない。

地域農業の底上げのための生産農家との目的共有や意思疎通の放棄
即席パッケージ型の大型直売所づくりで欠落するのは、もう一つ、地域の農業を底上げするための生産農家との目的の共有と日々の意思疎通である。
そもそも新設にあたって生産者の意見などはほとんどまったく相手にされないということは先にも書いた。しかしそれだけでなく、その地域の地域農業の底上げのために、何を特産品として軸に置き、副軸にはどのような産品を置いて、どの時期に誰がどのように栽培し出荷するのか―こうした具体的な栽培出荷計画づくりとは無関係に、直売所が作られ、どこでどういう計算をしてはじき出されたのかわからない売上げ目標値なるものが設定されるのが常なのである。
まるで、いつでもどこでも、農産物は販売に必要なだけ存在しているかのような錯認があるのである。

もちろん、今のように「いつでもどこでも……農産物がある」と書き記せば、「そんなことは思っていない」と反論する人も多いはずなのだが、こと、大型直売所の新設を構想する場面になると、売るものは何があるのか?それをどう作るのか?とは無関係に、他店舗の実績などから類推して売上げ目標値が決まり、売り場面積が決まり、品で埋めること自体が大きな負担になる数多くの平台が用意されていくのが実情ではないだろうか?
時には、自分の店の棚を埋めることさえ実際には大変な困難を抱えているのに、さらに全国的な地場産食材集出荷システムに参画して自分の直売所をその集荷ポイントにして、外に出荷することを夢想しているような場合さえあるのである。

直売所はその出発点の頃に、いつも売るものが足りなくなってしまうという難問を抱えていた。それを克服するために、生産者に出荷依頼の電話をかけまくったり、車で取りに行ったり、さらには部会を組織して販売技術の向上を図ったり……様々な苦労を重ねてきた。いまでこそ30億円などという大きな額を売るようになった大型直売所も、出発点においては必ずこういう時代を経ているのである。そしてそれがあったからこそ、直売所は地域の農業を活性化させ農家を元気にする拠点となることができたのである。
いつの時期に、誰が何をどのように栽培し出荷するのか?―こういう具体論のレベルにまで降り立って農業振興計画づくりを積み上げていくことこそが、直売所の発展を支える大きなカギを握るのではないだろうか?
※本稿の写真はイメージです。本文とは関係ありません。
※この記事は「産直コペルvol.39(2020年1月号)」に掲載されたものです。