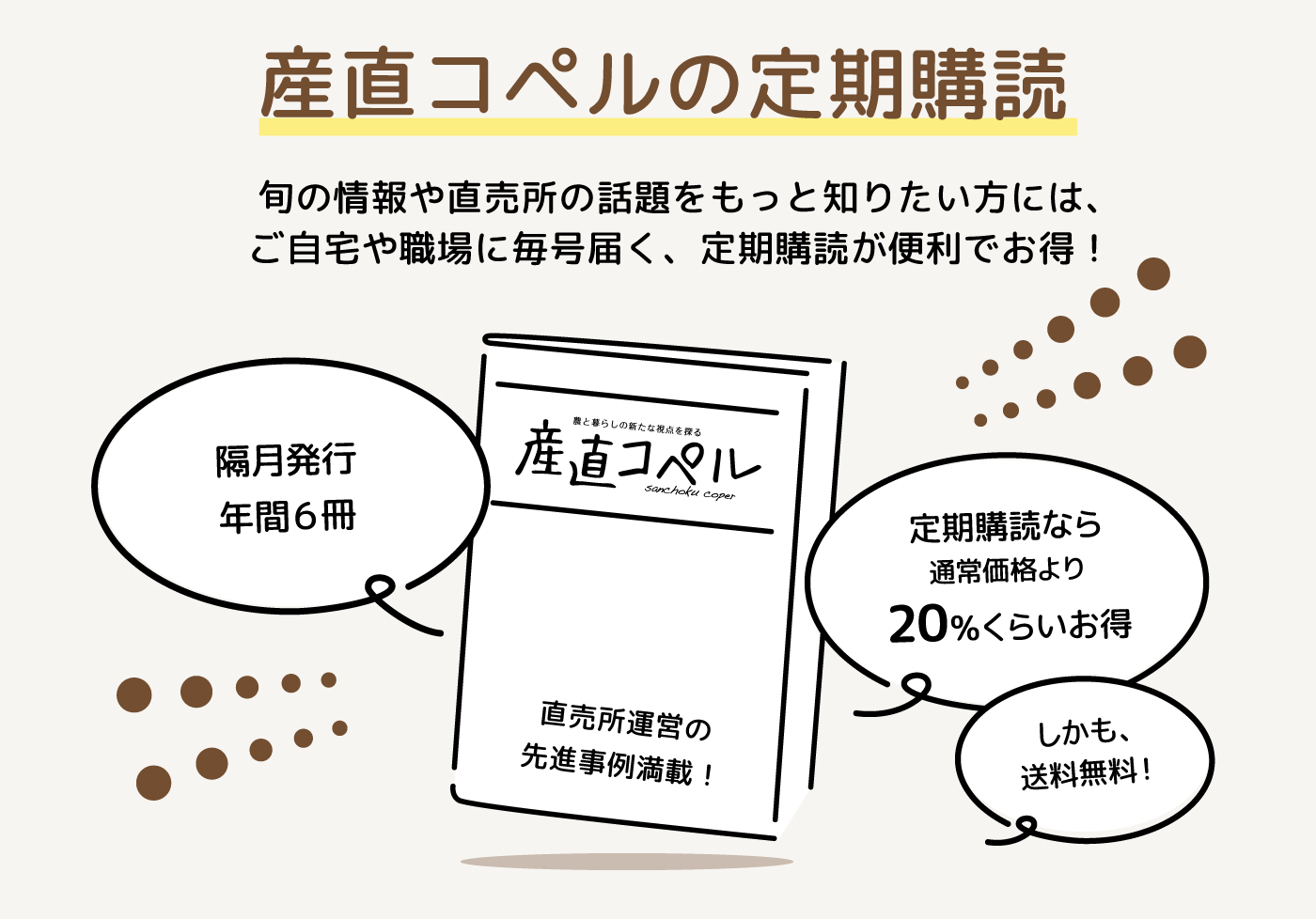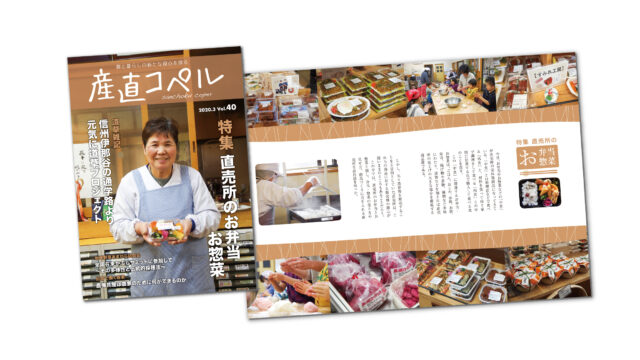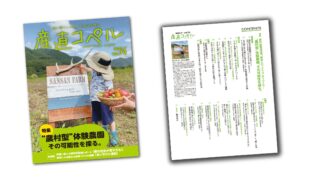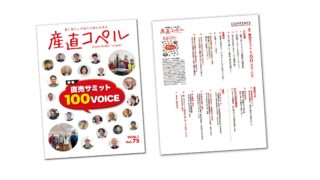滋賀県東近江市に店を構える「あいとう直売館」は、年間を通じて多彩なイベントを開催することでも知られる人気の道の駅だ。
開設は30年前。当初から「都市と農村との交流」を掲げ、道の駅開設と同時に体験農園もスタートした。同駅の大平健太郎駅長に、直売所が運営する体験農園のスタイルやそのメリットを伺った。(文・平尾なつ樹)
30年前から続く
さつま芋堀り企画
あいとう直売館で運営する体験農園は、大きく分けて2種類ある。1つは、道の駅に隣接する農園で行う、さつま芋の植え付けと収穫体験だ。
3メートル×1メートルの大きさの圃場を1区画として、全部で300区画を用意。利用者は、原則6月の植え付けと10月の収穫にのみ訪れ、その間の管理は「農業後継者クラブ(F.S.C.)」という名の地元農家組合の手で行われるという。利用料は、1区画につき2500円。毎年区画のほとんどが埋まるほど人気の企画だそうだ。
直売所では、予約の受付管理や案内状の発送などの事務作業を担っており、手数料として利用料の4分の1が直売所に、残り4分の3が後継者クラブの農家に支払われる構造だ。
「収益は、農業後継者クラブの皆さんの飲み代にもなってますよ」と大平さんは笑う。農業後継者クラブに属しているのは、それぞれ異なる品種を栽培する農家7名程度だというが、体験農園の管理作業は、彼らの貴重な交流・情報交換の場にもなっているそうだ。
 農業後継者クラブの皆さん
農業後継者クラブの皆さん利用者は、県内からの参加者が大半だが、遠いところでは大阪や名古屋、福井県などから訪れる人もいるという。
大平さんいわく、「そういう方(遠方からの利用者)は、この場所に来て『山を見るだけで癒される』なんておっしゃいます。その方たちにとっては、単純に芋掘り体験に来るのではなく、この場所までくることに意味があるんだと思いますね」。
直売所をオープンした30年前から続けているこの企画。地元の保育園では当初から30年間、毎年園児たちが芋植え・芋掘りに訪れているといい、さらに最近では、子供の頃にこの体験を利用していた園児が大人になり、所帯を設け子供たちと一緒に家族で参加するケースもあるそうだ。
事務作業の外注で
繁忙期の農家を助ける
あいとう直売館が運営するもう1つの体験農園は、直売所の出荷農家の圃場で行われる果物狩りだ。さくらんぼ、いちご、ブルーベリーの3種について果物狩りを受け入れている。直売所でチケット販売・受付・圃場までの案内等を行い、圃場管理や当日の利用者対応などは各出荷者が行うというやり方だ。
出荷者の一人であるいちご農家の方から、「いちご狩りを受け入れてみたい」という相談を受けたことをきっかけに、現在の、出荷者と直売所が協力して体験農園を受け入れるスタイルが始まったそうだ。
「出荷者の方にとっては最も忙しくなる収穫・出荷の時期に、受付などの事務作業を外部へ頼めるこのやり方は、喜ばれていますよ」と大平さん。入園時間をある程度制限したり、何人かの農家の圃場で交代制にして体験を受け入れるなどの工夫によって、出荷者が農作業する時間も確保しながら、農家の手取りアップにも貢献する。
 東近江市には30戸以上のいちご農園があり、いちご狩りに関してはライバルも多いそうだ
東近江市には30戸以上のいちご農園があり、いちご狩りに関してはライバルも多いそうだ直売所、利用者、農家 それぞれが
満足する体験農園をこれからも
こうした体験の募集は、新聞広告やプレスリリース、SNS等を利用した発信をこまめに行うことで、多くの利用者が集まるという。
冒頭で述べた通り、あいとう直売館では、体験農園の他にも、年間を通じて、ライブやフリーマーケット、ワークショップなどの多彩なイベントを展開しているため、SNSなどでその情報を追っている消費者も多そうだ。
「お子さんなんかを見ていると特に感じるのが、『自分の手で収穫することがこんなにも喜んでいただけることなのか』ということですね」と大平さん。逆に農家からしても、直接消費者と触れ合って、その喜びを間近で感じられることは、活力になっているようだ。
さらに、直売所側から見ても、体験で訪れた利用者の方々が店舗で買い物をしていく効果もあり、「採算はとれている」と大平さんは語る。
こうした体験には、家族連れで訪れる利用者が多いという、単純な農業の体験の場を提供するだけでなく、親と子、孫と子などの交流の場にもなっているということだ。
「これからもたくさんの方々に、土に触れ、収穫の喜びを体験していただきたいと思っています。消費者と出荷者とが交流し合える体験農園の場を維持していけるよう直売所として努力していきたいですね」と大平さんは笑顔で締めくくった。
農家の手取りアップと地域の活性化につなげるためにも、直売所と農家が連携して体験農園を運営するこの仕組みは、中山間地の小さな直売所でも、導入できる可能性がありそうだ。
 あいとう直売館には直売所のほか、レストランや、料理教室のできるキッチンスタジオ、手づくりジェラートの販売店なども併設しており、様々な体験が楽しめる施設だ
あいとう直売館には直売所のほか、レストランや、料理教室のできるキッチンスタジオ、手づくりジェラートの販売店なども併設しており、様々な体験が楽しめる施設だ※この記事は「産直コペルvol.72(2025年7月号)”農村型”体験農園」に掲載されたものです。農村型体験農園に関心のある方はこちらからお買い求めいただけます!