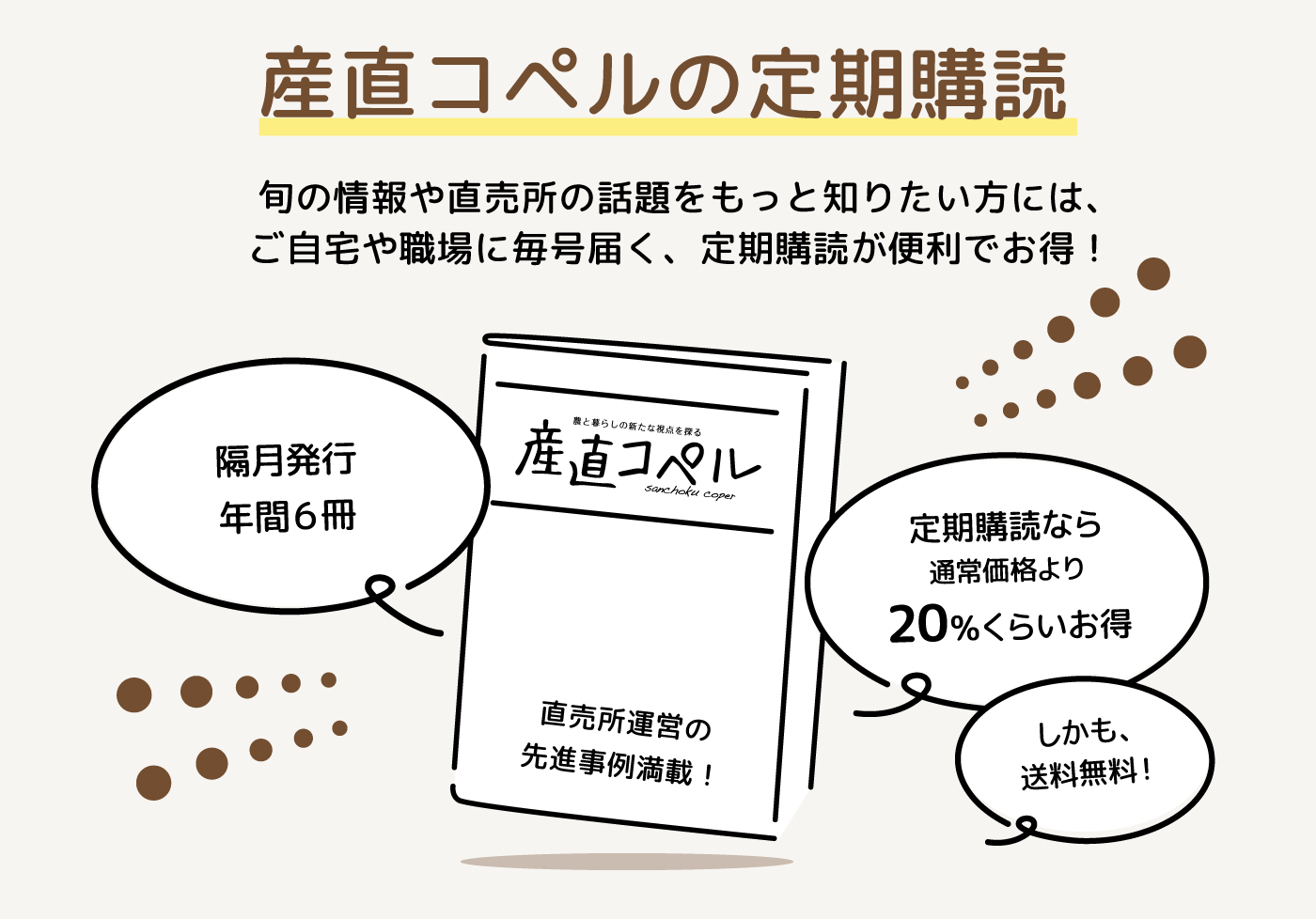長年、小誌編集長が全国各地を巡り、知り合った直売所創世記(第一世代)の人々。パイオニア精神にあふれ、個性豊かな彼らが率いてきた名物直売所が今、世代交代を迎えている。まさに今、その時期に差し掛かっている直売所、見事に実現した直売所を多角的に検証してみたい。

全国の直売所が世代交代期を迎えている
本号の『産直コペル』は豪華にも三つの特集を組んでいる。その一つめのテーマが直売所運営の継承。直売事業を運営する側の次世代育成と事業の継承がどのような局面にあるかに焦点を当てた。
小誌が、コロナ禍前に行った「直売所が直面する課題は何か」を問うアンケートで、運営側の後継者不在を挙げた回答は実に全体の7割近くに及んだ。人々の生活がかつての日常に近づき、コロナ禍もようやく終息に向かうかに見える現在においても、この状況に大きな変化はない。いやむしろ、深刻化したというべきかもしれない。
コロナ禍でも、地産地消の底力を発揮して売り上げを増加させた店は少なくない。しかし、逆にここで売り上げを落とし、経営状況を悪化させてしまった店もある。
その主たる要因としては―これは中山間地の中小規模の直売所ほど多いのだが―中心的運営者の高齢化と後継者の不在による経営困難が深まっていることが挙げられる。
成功パターンと困難パターン
もちろん規模の大小を問わず、経営者・運営者の世代交代を上手に成し遂げた直売所も数多い。その先進事例をこの特集の後半で3カ所取り上げている。安定的な経営体の下で、5年から10年という長期計画を立てて準備を進めてきたパターンや、数年間にわたる模索期間を経て経営体自体を再編し、その流れの中で世代交代を遂げたパターンなどがある。いずれも、大いに参考になると思う。
しかし、実際には、あの手この手を打ってはみたものの後継者候補が簡単には見当たらないという状況にある直売所が多いのが偽らざる実情であろう。
本特集では、広島県尾道市で創業以来20年にわたり地域の地産地消の拠点として活躍し、本年度の全国農林水産物直売サミットのホスト直売所の一つを務める「道の駅クロスロードみつぎ 野菜市」の生産者組織の綾目文雄会長と小吹悦司副会長に、創業以来の歩みを振り返りつつ、特に事業継承の面において実際のところどういった点で困っているのかを赤裸々に語っていただいた。同じ問題を抱える全国の仲間たちに向け積極的に問題提起をしてくれたお二人に感謝したい。
継承か、改革か― 腑分けが求められている
全国の直売事業は、1990年代初頭に姿を現すと、まるで燎原の火のように全国に広がっていった。それからおよそ30年。今、一つの転換期を迎えている。
この30年の間に直売事業は、系統出荷一本やりであったそれまでの日本農業に、低コストで旬の農産物を流通させるチャンネルを開き、農家に販売=生産主体としての意識の覚醒をもたらし、消費者と生産者が直接につながるコミュニティを生み出すなどした。これはまさに日本農業における一大イノベーションであったと言っても過言ではないであろう。
いまや、インターネットを舞台にした農産物直売事業がどんどんと広がっていることに示されるように、「農産物の直売」という概念は社会の隅々にまで広がり一般化している。これまで、「直売所の原則」(委託販売、低廉な手数料率、出荷・品質管理における決め事と自己責任の折り合い、出荷運営組合の団結やまとまり・協調性、公平と平等の原則……など)は、「新しい流れ」を支えるものとして掲げられてきた。しかし、いまや若い農家たちの事業展開の〝足かせ〟になっているように言われる場合もある。
そういう意見がすべて妥当だとは言わないが、それらをもう一度、今日的に見直して、何を継承し、何を改革するべきかをはっきりと腑分けするべき時が来ているように思われる。
「蛇が皮を脱ぐように」成長することが必要
東京大学で教鞭をとった著名な経済学者・故宇野弘蔵教授は、社会の変革は「蛇が皮を脱ぐように」進められなければいけないと言ったという。皮の内側の部分が新しい成長を遂げ、それを包み切れなくなった皮が古くなり、弱くなり、抜け殻となっていく。しかし、その皮に詰められていたエッセンスは、確実に新しい形となって脱皮を果たした本体に継承されている。社会はそういう風に内側に新しいものを創り出し、それが大きく膨らんで新しくなっていくべきだというのだ。 直売事業、いや具体的に言えば、一つひとつの直売所の運営体も、このように「新しいもの」に変わっていかなければいけないのではないか? 本特集がそのための一助になれば幸いである。
※この記事は、『産直コペル』vol.56(2022年11月号)に掲載したものです。